Exhibitors List
Exhibitors List出展者一覧
プラチナ
-
-

- キーサイト・テクノロジー
-
-
-

- 山洋電気
-
-
-

- コグネックス
-
ゴールド
-
-

- IDAJ
-
-
-

- STマイクロエレクトロニクス
-
シルバー
- 高砂製作所
- ブラザー販売
- プロテリアル
- サンエー電機
- マクソンジャパン
- MathWorks Japan
- 電研精機研究所
- コスモ石油ルブリカンツ
- TDK
- 日本シールドエンクロージャー
- 東芝デバイス&ストレージ
- ASPINA(シナノケンシ)
- EtherCAT Technology Group
- Tebiki
- Littelfuseジャパン
- ソリッドワークス・ジャパン
- KOA
- エイシーティ
- コーセル
- 諏訪三社電機
- YE DIGITAL
- eve autonomy
- Vicor
- 住友重機械工業
ブロンズ
- THK
- THK
- 大王電機
- 新光電子 ~FAULHABER~
- ハイウィン
- マグプロスト
- 総研電気
- ヘガネスジャパン
- VACUUMSCHMELZE
- JFEテクノリサーチ
- 光進電気工業
- 電子磁気工業
- ジャパンマグネット
- 青山モータードライブテクノロジー
- Fortior Technology(Shenzhen)
- 大分県電磁応用技術研究会/ブライテック/デンケン
- DINKLE INTERNATIONAL
- 加美電子工業
- 菊水電子工業
- スミダコーポレーション
- ルビコン
- Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association (TEEMA)
- RECOM
- テクシオ・テクノロジー
- ハル電子
- Luci
- 日本パナトロニック
- 双葉電気
- リゴルジャパン
- オータマ/e・オータマ
- マイクロウェーブファクトリー
- シャフナーEMC
- 森田テック
- 東洋メディック
- 日本イーティーエス・リンドグレン
- 日本オートマティック・コントロール
- JX金属
- 埼玉大学工学部機械工学システムデザイン学科制御工学研究室
- 香川大学 井上研究室/大阪大学 石塚裕己
- 慶應義塾大学 竹村研究室
- 東京工業大学 吉田研究室
- 横浜国立大学 佐藤研究室
- 香川大学 佐々木研究室
- 香川大学 井上研究室・大阪大学 石塚裕己
- 徳島大学 高岩研究室/岡山理科大学 横田研究室
- 大阪工業大学 フレキシブルロボティクス研究室
- GMS JAPAN
- T-Global Technology
- カワソーテクセル
- 加賀テック
- 東芝ホームテクノ
- ポニー電機
- グローブ・テック
- マウザー・エレクトロニクス
- 大陽工業
- プロトワーク
- イナック
- スタッフ
- ナミテイ
- 徳力本店
- イマジオム
- 枚岡合金工具/ネクストサイエンス
- ミナミダ
- テクノア
- インプローブ
- ITG Electronics
- 大同特殊鋼
- DMカードジャパン
- P-DUKE/シナダイン
- リケン環境システム
- Adapter Technology
- 葵製作所
- Orbray
- ケーメックスONE
- ハギテック
- 日本旭立科技
- COIL TECHNOLOGY CORPORATION/多摩パーツ
- 利送イーエムシー
- 武蔵野通工
- マイクロネット
- タイミー
- ナベルホールディングス
- Xiamen Faratronic
- Netrix SA
- シグレント
- cpc 八千代産業
- 青山特殊鋼
- ヒルシャー・ジャパン
- 山下マテリアル
- マクニカ/アナログ・デバイセズ
- トーアメック
- かがつう
- Vigor Precision
- エス・ジー・ケイ
- ネクスタ
- JFEスチール
- テクトロニクス
- 電子制御国際
- YTK
- 計測技術研究所
- UMEC
- 三美/SIGNAL Electronics
- 富士高分子工業/FUJIPOLY
- SAFTTY ELECTRONIC TECHNOLOGY
- ユニファイブ
- セールスワン
- アルファー精工
- Social Area Networks
- 日本パルスモーター
- 甲神電機
- スマック
- ニプロン
- SGSジャパン
- 安泰科技
- CMインダストリー
- アライドテレシス
- ソナス
- テクノシステム
- IHI機械システム
- AAポータブルパワー
- ワゴジャパン
- スマートコイル(東莞市鴻技電子)
- エーイーティー
- 竹内工業
- KEC関西電子工業振興センター
- バイオネット研究所
- 日本生工技研
- ブロードコム
- アジア電子工業
- ケイズ
- 利大渓工業
- 東莞市鑫惠展机電/東莞市道成電子
- Future Materialz
- 北川工業
- 法政大学 田中豊研究室
- 新光電子
- アイコムソフト
- SHT(エスエッチティ)
- プルス
- CHANG SUNG
- ナノコート・ティーエス
- ジェピコ
- タカハタプレシジョン
- キャディ
- キャディ
- アビリカ
- TDK
- ABB
- デバイスHILLTOP
- 日本電磁測器
- Earth Panda Advance Magnetic Material
- Ningxia Magvalley Novel Materials Technology
- Shenzhen Magnet Laboratories
- Baotou Tianhe Magnetics Technology
- TAILWIND INDUSTRIAL HOLDING
- NINGBO PERMANENT MAGNETICS
- INNUOVO MAGNET
- Ningbo Rieche Technology
- Ningbo Jinji Strong Magnetic Material
- Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology
- Ningbo Ninggang Permanent Magnetic Materials
- Ningbo Co-Star Materials Hi-tech
- Jiangsu Sanjiang Electic Group
- Zhejiang Rongxin Magnet
- Hangzhou ShengshiDeng Magnetics
- Maanshan CY Magnetic Technology
- Jiaozuo Zhenlin Magnet
- Ningbo Ketian Magnet
- NINGBO YUANCHEN NEW MATERIALS
- TianLi Electrical Machinery (Ningbo)
- SHANGHAI SAN HUAN MAGNETICS
- Ningbo Jinlun Magnet Technology
- Yantai Zhenghai Magnetic Material
- CHINA PEACE BUSINESS AND EXHIBITION
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度ポリテクセンター
- エーアイシーテック
- コスモサウンド
- 深圳市ポコ新材料
- Hengdian Group DMEGC Magnetics
- TDG HOLDING
- 岡谷電機産業
- VCCI協会
- 科学情報出版
- Quadcept
- ファナック
- ザワード
- U-MAP/岡本硝子
- 英知コーポレーション
- Degson Technology
- 鳥羽洋行
- アドバンテスト
- レムジャパンアドバンテック
- ニチコン
- インコム
- 浜松ホトニクス
- パナソニック システムネットワークス開発研究所
- 日幸電機
- テクノサイエンスジャパン/テクノサイエンスシステムズ
- 東陽テクニカ
- エレナ電子
- 岡山大学 竹本研究室
- 徳島大学 高岩研究室/岡山理科大学 横田研究室
- 岡山大学 システム構成学研究室(神田・脇元・山口)
- 岡山大学 インターフェースシステム学研究室
- 東京工業大学 金研究室
- 東京工業大学 鈴森研究室
- アドバンスドナレッジ研究所
- セミクロン
- Shenzhen BASiC Semiconductor
- アーク
- エスケーファイン
- マツダ
- エースポイントシステムズ
- バリューテクノロジー
- アスプローバ
- 水戸工業/日本サイトラインシステムズ
- 東芝デジタルソリューションズ
- ハイバーテック
- テクノア
- 日立ケーイーシステムズ
- トビー・テクノロジー
- ビジネス+IT (SBクリエイティブ)
- ティー・テクノロジー
- 横河計測
- Skip Motor Inc
- 小野測器
- CYSTECH ELECTRONICS
- 金陽社
- エルテック
- Celanese Micromax
- 信越化学工業
- エクセディ
- 松定プレシジョン
- Vision Technologies co.,ltd
- マクセル
- アポロ精工
- 山陽特殊製鋼
- 東邦亜鉛
- シーイーシー
- 創造デザイン
- ファクトベース
- ストラクト
- 日産自動車 日産コンサルティング
- デンソーEMCエンジニアリングサービス
- NPMハイテクノロジーズ/Netzer
- サイバネットシステム
- インキュベーション・アライアンス
- 旭精機工業
- Dongguan Jiarun Yaoguang Industry
- 日伝
- インフォメーション・ディベロプメント
- シーメンス
- ハセテック
- Profil Gate
- 沖マイクロ技研
- エイシング
- 長瀬産業
- マツイ
- 東洋精密工業
- ビジー・ビー
- 日本ケイデンス・デザイン・システムズ社
- タカヤ
- テクロック・スマートソリューションズ
- スマート・ソリューション・テクノロジー
- CBRTI
- 菅原研究所
- ELMA/摂津金属工業(アイデアルトランク)
- アンシス・ジャパン
- ナパック
- SystemBase
- Wemake
- ものレボ
- ディ・エス・シィ
- 京セラ/サーモグラフィティクス
- シチズンファインデバイス
- 大興電子通信
- フレクシェ
- dSPACE Japan
- エヌ・ディ・アール
- 日本ケミコン
- フェイス
- アジャイルウェア
- 塚田理研工業
- 三協インターナショナル/江蘇三協アルミ
- Littelfuse IXYS / ジェイレップ
- 第一実業
- ダイナカスト
- パナソニック インダストリー
- ミロクリエ
- 凸版印刷
- シーレックス
- 凸版印刷
- LIGHTz
- 桜井
- パナソニック インダストリー
- バーナードソフト
- タワシテック
- ACTUNI
- シーラックス
- Piezo Sonic
- 瑞穂
- ノイズ研究所
- ディーシージェイ
- 構造計画研究所
- ヤマト科学
- NTTアドバンステクノロジ
- 岩崎通信機
- フォトロン
- 積乱雲プロジェクト
- MODE
- 日本コントロールシステム
- ゼネラル物産
- 帝国インキ製造
- 百識電子テクノロジー
- 東北エンタープライズ
- SecondSight
- ナブテスコ
- 東京工業大学 千葉・清田研究室
- knewit
- イーアールアイ
- 近畿大学 ソフトロボット制御学研究室/香川高専 門脇研究室
- 近畿大学 ソフトロボット制御学研究室/香川高専 門脇研究室
- Chroma ATE
- Lead Year Enterprise
- Ferrico Corporation
- Yeng Tat Electronics
- HTP ASIA TECHNOLOGY
- MAX ECHO TECHNOLOGY
- スターライト工業
- 三ツ波
- キーエンス
- レステックス/テックマンロボット
- 三桜工業
- エヌエフ回路設計ブロック/NF千代田エレクトロニクス/NF計測技研/エヌエフホールディングス
- シーマ電子
- ヨクスル
- テレダイン・レクロイ
- ナカヨ
- SHENZHEN JEWEL ELECTRONIC&TECHNOLOGY
- ベルニクス
- システム計画研究所
- 日本ツクリダス
- 東京都大田区
- レボーン
- Guizhou Space Appliance/Ningbo Fuxing Shaft Industry
- デンケン
- HTM Hydro Technology Motors
- Chengdu Galaxy Magnets
- Dongguan Jiarun Yaoguang Industry
- 上海キングマグネット
- NINGBO COCOMAG INDUSTRY
- Huzhou Yueqiu Motor
- ANHUI HANHAI NEW MATERIAL
- CHANGZHOU JINKANG PRECISION MECHANISM
- ZHENJIANG JINGANG MAGNETIC ELEMENT
- Shenzhen Envision Motor
- ピーバンドットコム
- モーションリブ
- インプレス
- 岡田商事
- 日本シイエムケイ
- 日本コンピュータ開発
- Skillnote
- さくら教育支援グループ
- レスターコミュニケーションズ
- オプトサイエンス
- ケーエムケーワールド
- 電波新聞社
- クロニクス
- ブリヂストン ソフトロボティクス ベンチャーズ
- FSP TECHNOLOGY
- トーキン
- 東京電子工業
- FLOSFIA
- 神奈川県企業誘致促進協議会
- Hitec Multiplex Japan
- タカノ
- OKIネクステック
- エフ・シー・シー
- 日経ビーピー
- TUNG-HO MOLD INDUSTRY
- SIN-G PRECISION
- イーエムワークス・ジャパン
- Qingdao One Magnet Electronic
- XIANDENG HI-TECH ELECTRIC
- Suzhou Fine-stamping Machinery Technology
- NINGBO ZHENYU TECHNOLOGY
- リュウジカギ
- QINGDAO YUNLU ENERGY TECHNOLOGY
- UPTEC Intelligent Manufacturing (Wuxi)
- ユーザベース(SPEEDA R&D)
- 三洋貿易
- オータマ校正サービス
- SCSK(m-FLIP)
- SCSK(atWILL)
- タキロンシーアイ
- ONES JAPAN
- WELCON
- フツパー
- 日刊工業新聞
- T Project
- 日本能率協会コンサルティング
- トキコシステムソリューションズ
Webinar
Webinarウェビナー(出展者ウェビナー・主催者講演)
出展者ウェビナー・主催者講演を聴講ご希望の方は、来場者登録をお願いいたします。
出展者ウェビナー
-
- WBGパワーモジュール動特性評価とシミュレーション
- キーサイト・テクノロジー
ワイドバンドギャップ(WBG)パワーモジュールにおいて、高速動作・低損失といった特性を示すため、動特性評価の重要性が増してきています。しかし、動特性測定の再現性、安全性に課題があり、評価やデータ解析にも時間がかかっていました。本セミナーでは新製品PD1550Aがどのようにこれらの課題を解決するかについてお話しします。またデバイスモデリング、回路シミュレーションへの応用についてもご紹介します。
-
- 最適なファンの選び方・使い方セミナ~ファンモータの基礎~
- 山洋電気
▼ こんな方におススメです
・はじめてファンを使用される方
・ファンの基礎的な内容を知りたい方
▼ウェビナー内容
・ファンの役割と使用例
・ファンの種類
・ファンの風量と静圧
・ファンの電流と音圧レベル
・ファンの期待寿命 -
- AIを圧倒的なスピードで 画像システムで解決する高速な生産ラインの検査課題
- コグネックス
コグネックスのIn-Sightシリーズから史上最強のオールインワンモデルが新発売されました。
誰でもカンタンに使えるAI "エッジラーニング"のツールセットとルールベースの組み合わせが、OK/NG判定のようなシンプルな検査から、ロボットガイダンス等の複雑なアプリケーションまでを一台で解決。高速な生産ラインの検査課題を解決します。
◎エッジラーニング画像システムIn-Sight 3800の3つの特徴
・カンタンAI+ルールベースで幅広い検査を1台で
・少ない画像枚数で、たった5分で学習完了
・目視の限界を超える検査スピードと正確性
是非、本ウェビナーをご視聴ください。 -
- DEMINTASNXとSimcenter Flothermを連成したノイズと熱の最適化設計
- IDAJ
基板設計においてはEMIノイズ対策と熱対策の両方が必要で、いずれの要件も満たさなければなりません。しかし、それぞれの対策がトレードオフの関係になることが多く、両立させることが難しいという課題があります。本発表では、EMI抑制設計支援ツール DEMITASNXとSimcenter Flotherm、modeFRONTIERを使用して、EMIノイズと熱の協調設計の手法をご提案します。
-
- さまざまな省電力ニーズに対応!STの最新高電圧IPM & SiCパワー・モジュール
- STマイクロエレクトロニクス
電力消費の抑制は、地球温暖化防止やエネルギー価格上昇のリスクによって全世界的なトレンドとなっています。STは、このような省電力化ニーズに対し、最新技術を活用したインテリジェント・パワー・モジュール(IPM)やパワー・モジュールを提供しています。本セミナーでは、ファン・モータや生活家電、サーボ・モータ、インバータなどに使用され、3相ドライブ製品の設計簡略化や消費電力削減に貢献するIPMに加え、より高電力の産業ドライブやパワコンなどに最適で、従来のIGBTと比べて高性能なSiC MOSFETを使用したパワー・モジュールの最新製品について解説します。
-
- モデルベースデザイン(MBD)でモーター制御を設計し実装する方法
- MathWorks Japan
脱炭素化社会の実現を目指した取り組みが活発化し、従来技術の置き換えが進んでいます。
モーターは省エネルギー性能が高く使い勝手が良いことから、今後ますます需要が増加していくと言われています。
本セッションでは、永久磁石同期モーター(PMSM)の「ベクトル制御」の設計から実装までをシミュレーション技術を利用し、業務の効率を高める方法をご紹介します。モデルベースデザイン(MBD)のワークフローにおいて、MathWorks社が提供するツールを適材適所で活用することで開発の効率化が図れます。
モーター制御設計に関心のある方やモーター制御関連の業務に携わっている方必見です。 -
- 〜ノイズ対策の現場で得られた〜 ケーブルへのシールド実践技術
- 電研精機研究所
ノイズトラブルの現場ではケーブルにシールドを施す機会が多くあります。その結果、ノイズ障害が悪化、変化しなかった現場もあれば劇的に改善した現場もあります。これらの要因には「シールドの末端接続」が関わる問題や現場環境の違い等が考えられます。当初、シールドの末端接続はループを形成しないよう、片端だけを接地やグランドに接続していました。しかし、ある現場で片端接続にも問題が確認された為、それまで禁止していた両端接続を再検討し、施工方法も変更しました。結果、多くの現場で成果をあげています。本セミナではシールドの末端接続の問題点と両端接続を可能にしたケーブルへのシールド施工方法について手順を追って解説します。
主な内容
ケーブルのシールドと接地・グランド
シールドの末端接続(片端/両端)
ノイズのモード変換
インバータ・サーボ機器のためのシールド
※テキストは弊社製品ページより入手可能です。 -
- 水冷・伝導冷却電源の放熱設計事例
- コーセル
■電源放熱の必要性・背景
近年、CO2削減やカーボンニュートラルが叫ばれる中、製品の省資源化、環境対応が重要になってきています。スイッチング電源は、省スペースでより多くの電力を供給するために、電源の電力密度が向上しています。そんな電力密度が向上したハイパワーな電源を使用するにあたり、電源から発生する熱を上手に逃がす必要があります。
本ウェビナーでは、電源の放熱方法の種類、放熱方法の選択例、電源の放熱設計事例をご紹介します。
■電源放熱方法の種類
電源放熱方法の種類をご紹介します。
■用途に合わせた放熱方法の選択例
用途に合わせた電源放熱方法の選択例をご紹介します。
■電源放熱設計事例の紹介
パワーモジュール電源における筐体放熱設計事例や水冷板を用いた放熱設計事例をご紹介します。 -
- Vicorの最先端電源モジュールで解決する、xEVの最新の電源課題
- Vicor
モジュールで構成する電動車の電力供給ネットワーク構成例や、800V化するxEVの400V系との互換性課題を解決する最新のDC-DCコンバータについて解説します。
※登壇者の都合により、登壇者・講演テーマが変更になる場合がございます。(法人の種類、敬称略)
主催者講演
経営戦略
-
- 未来起点 × 人間中心で考える
パナソニックのデザイン -
パナソニック ホールディングス
執行役員臼井 重雄

不確実性が高まり未来を予測することが困難な現代、私たちに必要なのは、ありたい未来の社会・くらしのかたちを自らで描き、未来を丁寧に創りつづけていくことではないでしょうか。パナソニックでは「デザイン経営」の手法を取り入れ、事業経営を既存の延長線上ではなく、長期視点で実現したい未来からリードする取り組みを始めました。その根底にあるのは「未来志向×人間中心」という考え方です。
- 未来起点 × 人間中心で考える
-
- 「地球を守り、火星を拓く
~CO2専門の独立系研究機関・CRRAの軌跡と未来~」 -
炭素回収技術研究機構
機構長村木 風海
・従来悪者扱いされてきた二酸化炭素が、地球上のあらゆる産業において貴重な資源となることが理解できる。
・二酸化炭素に関する研究開発は気候変動を解決するだけでなく、人類の火星移住も実現してしまう非常に夢のある研究であることが実感できる。
・脱炭素において、製品の直接CO2排出量だけを意識するのではなく、LCA(ライフサイクルアセスメント)の観点による行動が肝要であることを体感できる。
・講演終了後から、「二酸化炭素」と聞くとワクワクが止まらなくなる。温暖化は絶望ではなく、大いなるチャンスであると前向きに考えることができるようになる。 - 「地球を守り、火星を拓く
-
- スマートファクトリー構築の進め方
50のイメージセルがものづくりDXを具体化する -
日本能率協会コンサルティング
デジタルイノベーション事業本部
本部長毛利 大

本セミナーでは「各社のスマートファクトリー(以下SF)の姿は一つの筈はない。自社流のSFをどう構築するか」をテーマに話を進めて参ります。IoT,CLOUD,AI,5G。こうした技術革新によって、ビッグデータの瞬時の把握と意思決定のサポートが容易にできる時代、こうした技術を取捨選択しどのように自社のものづくりに生かしていけば良いのか。工場を取り巻く4つのチェーンから整理した「SFイメージセル」、イメージセルをコア技術とした、「TAKUETSU PLANT Design Method」。この弊社オリジナル技術を事例を交えてご紹介いたします。デジタル技術で恩恵を受けるのは、むしろ多くの中小企業です。本プログラムは会社の大小を問わず、自社流SFの道筋を描くヒントになると考えています。
- スマートファクトリー構築の進め方
-
- 業界別スマートファクトリー構築セミナー(自動車部品メーカー編)
50のイメージセルで具体化するものづくりDX -
日本能率協会コンサルティング
デジタルイノベーション事業本部 兼
経営コンサルティング事業本部
チーフ・コンサルタント戸張 敬介

近年、デジタル技術は急速な進化を続け、企業は、これらのデジタル技術やサービスを活用しながら、従来のビジネスモデルを問い直し、組織や業務そのものを変革しながら新たな価値を生み出していくことが求められています。
一方、少なくない企業から、「デジタル技術とものづくりの両方を組合せて考えられる人材が不足し、新たな突破がなかなか生まれない」といった悩みが寄せられ、業界や企業ごとに異なる「環境変化」と「ものづくりの特性」を踏まえたデジタル構想をいかにスピーディーに描くかが変革のキーとなりつつあります。
こうした状況を受けて、JMACで蓄積する「スマートファクトリー構築」の手法を土台に、業界ごとの「ものづくりDX」検討モデルに関する研究を進めてきました。
開発・設計プロセス、生産管理・物流プロセス、生産プロセス、ビジネスプロセスの4つのプロセスをつなぎ合わせた視点により、ものづくりの次なる飛躍を実現するイノベーションの手法をご紹介します。 - 業界別スマートファクトリー構築セミナー(自動車部品メーカー編)
日本のものづくり
(すごいだろ!)
-
- 昨年、大好評を得たウェビナーが再登場!
※内容は昨年公開した内容を同じものになります。
(8月1日~8月3日限定)夢持ち続け日々精進 -
AandLive 代表取締役髙田 明


社長自らが出演するテレビショッピングで人気を博した、ジャパネットたかた創業者の髙田明氏。佐世保の小さなカメラ店からスタートした同社が、全国に広く知られる企業になったのはなぜか。
経営者として、またテレビショッピングの顔として、同社の先頭に立って率いてきた髙田氏は、2015年に社長を退任した。退任後は、サッカークラブの経営という新たなフィールドへの挑戦など、常に“今を生きて”きた髙田氏の人生を振り返りながら、長きにわたるラジオやテレビ通販のMC経験をとおして感じた「伝えることの大切さ」などについてもお話しいただきます。 - 昨年、大好評を得たウェビナーが再登場!
-
- パナソニックの水素社会普及に向けた取組み
-
パナソニック
エレクトリックワークス社
電材&くらしエネルギー事業部
環境エネルギーBU
課長河村 典彦
パナソニックでは2009年から家庭用燃料電池「エネファーム」を生産している。
この技術を応用し、純水素型の燃料電池を2021年10月に発売した。その純水素型燃料電池の特長ならびにこの製品を活用したRE100実証施設「H2 KIBOU FIELD」について紹介する。 -
- 昨年、大好評を得たウェビナーが再登場!
※内容は昨年公開した内容を同じものになります。GaOパワーデバイス社会実装を進めるグローバル・オンリーワン企業 -
FLOSFIA
共同創業者 営業部 エバンジェリスト井川 拓人

酸化ガリウム(GaO®)は炭化ケイ素(SiC)や窒化ガリウム(GaN)等の従来のワイドギャップ半導体を超える大きなバンドギャップ値と、高い導電性をあわせもつ事から更なる低損失が期待される新規パワー半導体材料として注目されている。そのなかでもα型酸化ガリウムは、非真空プロセスである『ミストドライ法®』を使って製造された日本発の新材料であるが、本講演では弊社によるGaOパワーデバイスの実用化の状況、及び弊社の別事業として進めている埋め込み型パワーモジュールについて最新の状況を発表する。
GaO®・ミストドライ法®は、株式会社FLOSFIAの登録商標です。 - 昨年、大好評を得たウェビナーが再登場!
-
- 昨年、大好評を得たウェビナーが再登場!
※内容は昨年公開した内容を同じものになります。「ロボット学」と「人とロボットの協働社会」 -
日本ロボット学会(IHI)
(技術開発本部)
会長(技監)村上 弘記

ロボットが開発されてから約50年、ロボット学会設立から40年となっていることからロボットの研究開発の歴史を振り返る。近年、Society5.0が推進されている中で、Cyber Phisical Systemとして重要なロボットの新しい活用が期待されている。社会実装では、中・韓や欧州が先行している状況で日本のこれからの方向性について語りたい。
- 昨年、大好評を得たウェビナーが再登場!
-
- 設備故障ゼロに向けた保全管理や予兆保全の取組み
〜基盤を固めて攻めの設備保全で実現する生産コスト削減〜 -
日産自動車
IP顧客ビジネス開発部野水 靖二/河野 稔
生産ラインのトラブルによるコスト上昇、納期遅れ、品質不具合は発生していませんか?
コスト上昇、納期遅れ、品質不具合を出さないためには、設備の安定した稼働が必要です。
保全活動における設備信頼性向上は利益を生み出す生産活動の基盤です。
下記、4つのポイントで解説します。
・設備故障ゼロに向けた保全の全体的な進め方として、5つのステップで解説します。
・5つのステップでは、故障しない設備づくりにおいて独自の仕組み構築や、ワンランク上の故障解析力を身に付け、強い現場力を実現する方法を解説します。
・仕組み造りや、仕組みの運用、改善ができる人財育成を事例をもとに解説します。
・定期点検では、防ぎきれない故障に対して、予兆保全への取り組みを解説します。
戦略的なアプローチで効率的な維持管理体制の構築を行い、設備故障ゼロを実現します。 - 設備故障ゼロに向けた保全管理や予兆保全の取組み
技術系トピック
-
- 最新組込みAI技術動向
~クラウドを使わずに学習可能なオンデバイス学習技術~ -
ローム
LSI事業本部 回路技術開発部
技術主務西山 高浩

AIは、クラウドからエッジ、組込みデバイスへと広がりをみせています。
組込みデバイスにAIを導入するとどんなことができるようになるのか、について解説します。
そして、現状の組込みAIのかかえる問題点とそれらを解決する最新技術であるオンデバイス学習についてご紹介します。 - 最新組込みAI技術動向
-
- 水素社会の未来を見据えデンソーが挑む、水電解装置「SOEC」開発
-
デンソー
環境ニュートラルシステム開発部
システム開発室
室長中島 敦士

デンソーでは、車載部品生産で培ったセラミック、熱マネジメントの技術を利用してSOECの実用化に取り組んでいます。本講演では、開発経緯、貢献領域、開発の状況を説明させて頂くと同時に、実用化に向けて共同開発や実証への期待についても解説させて頂きます。
-
- 設備保全DX事例とDX人材の育成活動の紹介
-
デンソー
生産調査部TPM改革室
課長石盛 正人

当社では新設設備の高度化と既存設備の長期間稼働による設備維持の難しさによって保全員の役割が増大、業務の効率化が大きな課題となっている。
そこで当社では設備保全DX化に取組み保全業務の効率化を進めてる。
本発表ではその活動事例と課題、導入に必要な人材育成事例について紹介する。
技術系(リカレント教育)
-
- 「日本半導体産業の復活」は誤認識
日本の半導体産業政策への提言 -
微細加工研究所
所長
CEO湯之上 隆
目次
・「日本半導体産業の復活」は誤認識
・改正法による補助金投入で日本半導体のシェアは上がるのか
・2兆円の補助金で2030年までに15兆円の売上を実現できるか
・ラピダス、「2027年までに2nmを量産」なんてできっこない
・日本は「強いものをより強くする」政策を実行するべき - 「日本半導体産業の復活」は誤認識
夏休み企画 JMAx日刊工業新聞
(リカレント教育)
-
- 社会と時代に合わせて変わっていく自分自身のために
~社会人の学び直し -
日刊工業新聞社
論説委員兼編集委員山本 佳世子
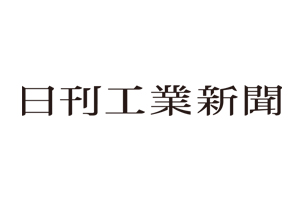
社会人の学び、学び直し(リカレント)教育は、18歳人口が減少する日本のすべての大学にとっての関心ごとだ。これまでは企業や官公庁など多忙な社会人にとっては、費用対効果など今ひとつだったが、状況は急速に変わっている。新型コロナウイルス感染症による社会の価値観の変化、デジタル革新(DX)や人工知能(AI)などの展開から、「今までの続きでは、魅力的なキャリアを築けない」という認識が浸透しつつある。
もっともリカレントの形はさまざまだ。企業など組織が構成員の学びを後押しするもの、1企業というより産業界の変化に連動したもの、転職を含む個人のキャリアアップを目指すもの、国際的な活動の中で信頼性を得るための学位取得などがある。
実は大学・産学連携の専門記者である講演者も、40代で大学院博士課程に社会人入学をし、その大変さに何度も涙している。大学リカレントの最新事例から、聴講者へ活動のヒントを提供したい。 - 社会と時代に合わせて変わっていく自分自身のために
-
- 超ヒマ社会は学び続ける社会
-
iU
学長中村 伊知哉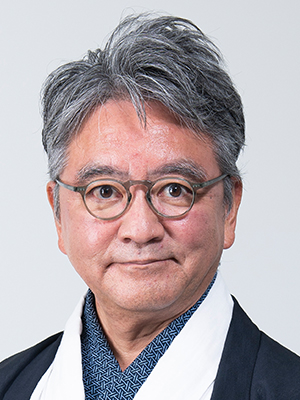
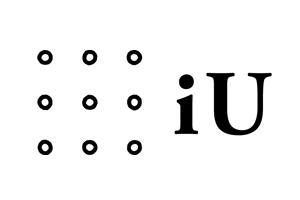
25年のデジタル化、10年のスマート化を経て、AIとロボットによる超スマート時代が来た。賢いAIと有能なロボットが仕事をこなす。となると、われわれは「超ヒマ」になる。働き方よりも遊び方が大事になる。そのためにはまず彼らを使いこなす能力を身につけなければならない。
機械が人の能力を超える時代は法則のない世となる。唯一確かなのは「変化する」ということ。変化を楽しむ人のみが生き残る。それは不断に学び続けなければならない時代でもある。リスキリング=学び直し、ではなく、エバースキリング=学び続けること、が必要だ。
コロナとの戦いで世界のDXが一気に進んでいる。ウクライナはデジタルが主戦場となった初の戦争だ。コロナとウクライナ、まだ2つの戦争は継続中で、戦後には新しいデジタルのステージが待つ。そしてそこはAIとロボットが占める空間でもある。超ヒマ社会を展望し、学び方を考える。 -
- 「正解」のない世界を生き抜く!ビジネスパーソンのための教養科目「世界標準のSCM」
-
オペレーションズ・マネジメント・グループ
代表行本 顕

「サプライチェーン・マネジメント(SCM)」の標準化を半世紀にわたり先導する米ASCMの実務家教育について、『基礎から学べる!世界標準のSCM教本』の著者が解説する。
サプライチェーン(供給網)はどの産業にも存在し、モノやサービスを供給する諸活動の連鎖であると同時に、意思決定の連鎖である。背後にあるのは、絶え間なく変化する需要と供給、そして無数に存在する選択肢だ。
SCMとは、この不確実で複雑なエコシステムの中で需給をバランスさせ、維持することでエコシステムが生み出す価値をより大きくするための活動といえる。
分業を基本とする現代においてSCMが効果的であるためには、組織の壁を越えた情報の可視性と、当事者間の概念共有が極めて重要になる。教育分野としてのSCMは実務家コミュニティによって知見が体系化された。
ビジネスパーソンが自ら作りあげた、ビジネスパーソンのための「共通言語」といえる。
本講演では、その「観点」を中心に解説する。 -
- 夏休みの自由研究にも使える
生分解性プラスチックの抽出を通じて身近な化学変化を学ぶ -
東京都立産業技術高等専門学校
准教授豊島 雅幸

我々の身の回りに存在する材料は大きく分けて、金属材料とプラスチック材料がある。
プラスチックは一般的には石油由来の同一構造が繰り返し結びついている高分子物質のことで、その軽さや安定性、加工のしやすさ、様々な機能の導入が容易であることなどから多方面に利用されているが、安定性ゆえに分解されにくい。
解決策として、微生物の働きで分子レベルまで分解することが可能な「生分解性プラスチック」がある。特に天然由来の物質で構成されるバイオポリマーは資源枯渇の恐れがなく、また二酸化炭素排出を制御できる環境に配慮した素材であることから、今後様々な展開が期待されている。
本講演では、納豆からアミノ酸であるグルタミン酸が連続してつながっている、「ポリ-γ-グルタミン酸」の抽出を実演する。その中で、実験手順で起こる化学反応の解説を通じて、普段の生活における豆知識を化学的見地から解説し、化学に対する興味や気づきを提供したい。 - 夏休みの自由研究にも使える
※登壇者の都合により、登壇者・講演テーマが変更になる場合がございます。(法人の種類、敬称略)

